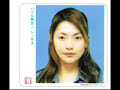菊池恭二 2/6
 〈COLEZO!〉沖縄島唄 バラード・コレクション |
1~5曲目と11曲目が普久原恒勇作曲。7がその父普久原朝喜の有名な曲で、残りは沖縄民謡3曲、八重山民謡3曲。本当に普久原恒勇のメロディーって美しい。個人的には特に玉城一美の「御縁花」と伊波智恵子の「歌や歌」はそれぞれの可憐な声と相まってとても好きです。ウチナーポップから深い民謡の世界へと入ってゆく橋渡しになる一枚になるのでは?(少なくとも私にとっては)。 |
 宮大工棟梁・西岡常一 「口伝」の重み |
第一部では、氏がどのように生きたきてか、どんな魂を持っていたかが読み取れます。
第二部では、氏の生き方を直に感じた人達の話が書かれており、氏だけではなく氏に関係してきた人達の話も読むことができ、私の中で最も心に残ったものでした。 |
 宮大工の人育て (祥伝社新書 104) (祥伝社新書) |
著者は、法隆寺の鬼と言われた伝説の宮大工、故・西岡常一棟梁のもとで
薬師寺金堂などの建立にかかわってきた宮大工。 気取りのない、淡々とした文体。押しつけがましくない内容。 基本は「教えない」ことだと言う。手取り足取りだと、自分で考えようとしない。 「なぜこうなるのだろう」と弟子がうずうずしてくるのを待つ器量が必要だと。 私はかつて部下に何でもかんでも教えようとしていたことがあった。 しかしあるきっかけで、「とにかく、オレがやっていることを見ていてくれ」 という接し方をするようになった。 ただこのやり方だと、時間がかかる。 いわゆる徒弟制度のようなものだから、マニュアル化できないのだ。 だから私の場合、決してうまくいったとは言えない。 だがそもそも、とくに「モノをつくる」場にいる場合、マニュアルでは処理できないことが多い。 いま、「職人」が見直されているとも聞く。 すべての人材育成に当てはまるかどうかはわからないが、 少なくとも多くの気づきのある本である。 たとえば、「いい職人は道具を粗末にしない」「大事なのは、その仕事を好きになれるか」――など。 当たり前と言えば当たり前なのだが、著者の言葉には不思議な重みがある。 もちろん、職人さんや、ものづくりに携わる人以外の一般社会人には そのまま当てはまらないこともある。 だが無理に当てはめて考えようとしなくとも、職人の世界を垣間見るつもりでいいと思う。 もう少し前に読みたかった本である。 |
人気動画
|
Loading...
|